「新学期が辛い」と感じる理由|心のSOSサインと対処法を紹介
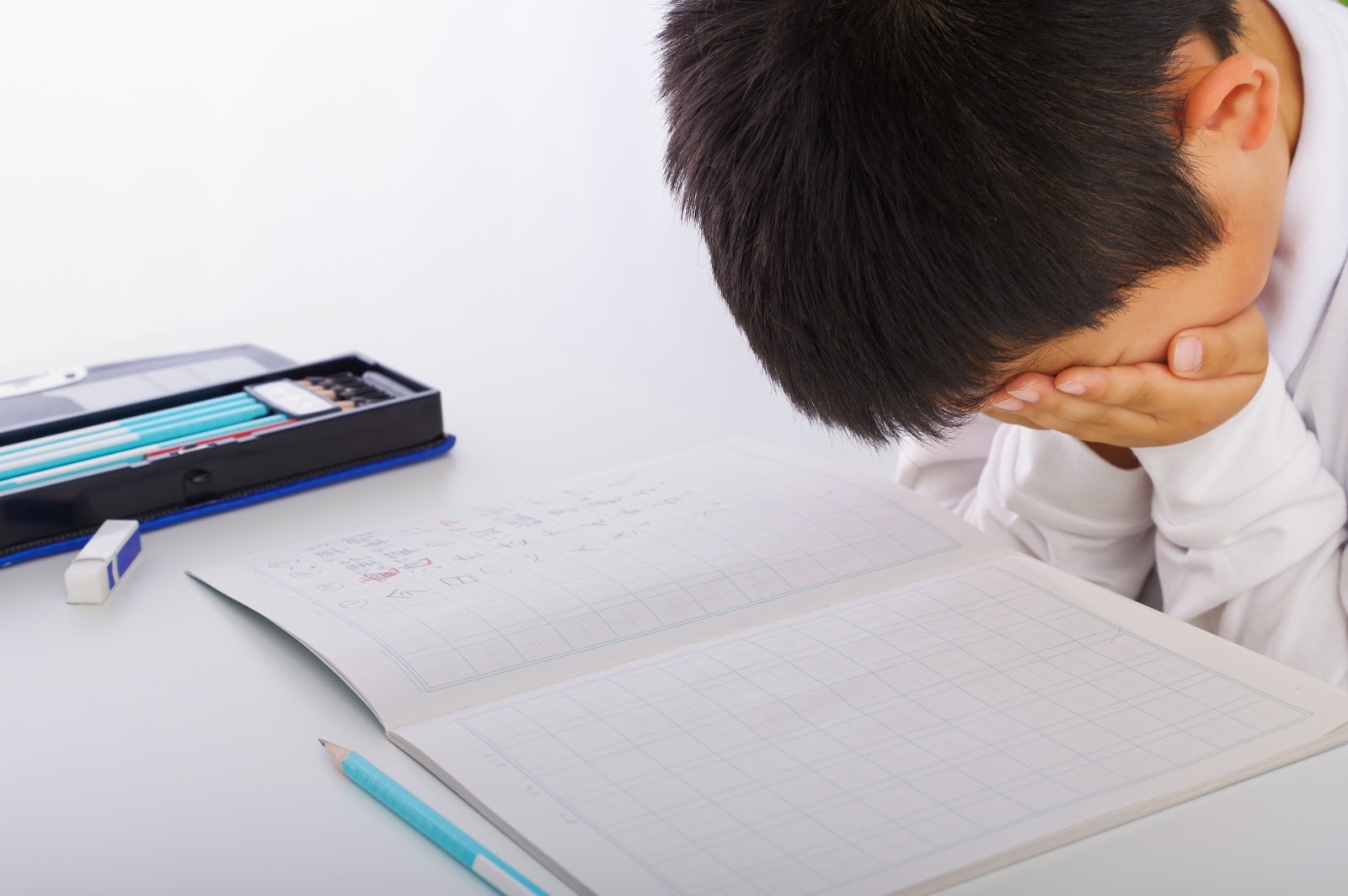
新学期が始まると、子どもは普段とは異なる環境に直面するため不安や緊張を抱きやすくなります。特に新学期や新しい学年への進級による勉強内容の変化や、それに伴うクラス替えや担任の先生の変更などはお子さんの心の負担となり、疲弊してしまう恐れもあります。その際には親御さんがいち早くお子さんの変化に気づき、適切なサポートをしてあげるのが大切です。
本記事では、新学期に子どもが感じやすい不安の原因や心のサイン、家庭でできる対応策を分かりやすく紹介します。
新学期が辛く感じるのはなぜ?
お子さんが新学期に不安を覚えるのは、さまざまな心身の変化に適応しきれないことが背景にあります。環境、対人関係、生活リズム、学業など複数の要因が重なると負担は大きくなり、登校をためらう気持ちにもつながってしまいます。それでは、原因を一つ一つ具体的に見ていきましょう。
環境の変化によるストレス
新しいクラスや担任、教室の雰囲気など環境が一新されると子どもは無意識に緊張を抱えます。環境が突然変わるのは心の安定を乱す大きな要因となるので、慣れるまでは負担を感じるのが当たり前だと考えておきましょう。
友人関係に対する不安
小学校から中学校への進学など新しい人間関係を築かなくてはならない際は、特に大きなエネルギーと勇気が必要です。そうでなくてもクラス替えで仲の良かった友達と離れたなど孤立を感じる状況では、登校への抵抗感が高まりやすくなるでしょう。大人にとってもそうですが、もちろん子どもにとっても人間関係は大きなストレス源となります。
生活リズムの変化
乱れた生活リズムを学校の時間に合わせて戻すことは身体にも精神にも負担がかかります。特に長期休暇後に早起きや授業に集中する習慣を取り戻すのは大きな負担がかかるため、疲れやすくなったり、イライラを感じやすくなったりするでしょう。目眩や発熱など体調不良を訴える場合もあります。
学業面でのプレッシャー
新学期の授業についていけるか不安に感じるお子さんは少なくありません。文部科学省委託事業の報告書によると、「最初のきっかけとは別の学校に行きづらくなる理由」(複数回答)の項目で「ある」と回答があった児童生徒のうち、「勉強が分からない」(小学生31%、中学生42%)との回答が最も高い割合でした。
特に前学期の学習内容に不安がある場合はプレッシャーとなり自己否定感につながりやすく、登校の妨げになります。
参照:不登校に関する基礎資料
関連記事:不登校 新年度を迎える子どもたちの心理
子どもが見せる心のSOSサイン
学校がつらいと感じている子どもは、言葉にせず行動や体調の変化で心の不調を表します。日々の様子に目を向け、「いつもと違う」と感じたら、それはお子さんからのSOSかもしれません。ここでは見逃してはならないサインを紹介します。
身体の不調を頻繁に訴える
心の不安は体の不調として現れることがあります。頭痛や腹痛、だるさや吐き気などが続く場合、それは登校を拒む理由のひとつとなっている可能性があります。見た目では分からない心のサインの1つとして日頃からよく観察しましょう。
睡眠リズムや食欲が大きく変化した
睡眠や食事は心の状態を映す大事なバロメーターとなります。特に夜更かしをしてしまい朝起きられない、寝すぎてしまう、急激に食欲がなくなったなどは心の疲れを反映しています。お子さんの生活のリズムが崩れ始めた際はいち早くそれを察しましょう。
感情の起伏が激しい
学校に行けないことへの葛藤や周りからのプレッシャーが原因でささいな物事で怒ったり、泣き出したり、時には乱暴になったりする可能性もあります。
これはお子さんの心が限界に近づいているサインです。この症状はいったん落ち着くこともありますが、その後に無気力な時期が続くことがあります。こうなる前に、いつもと違う情緒の変化があるのを見逃さないようにしましょう。
以前好きだったことに興味を示さなくなった
趣味や遊びに対して無関心になったときは、心のエネルギーが低下しているとのサインです。お子さんが少し前まで楽しくやっていたものに対し興味を示さなくなったら、心が疲れているサインとして早めに気づいてあげましょう。
生活習慣が乱れている
起床・就寝・食事などの基本的な生活習慣の乱れは心の不調と密接に関係しています。夜熟睡できているか、勉強に集中できているかなどを日頃の家庭内の様子から感じ取り、できていないと感じた際はなるべく早めにサポートを始めましょう。
「新学期が辛い」と感じている子どもに親ができることは?
お子さんが「学校に行きたくない」と訴えたり、逆に何も話してくれなくなったりした際、親としてどう関わればよいか戸惑うこともあるでしょう。まずはお子さんの気持ちに丁寧に寄り添いながら、無理をさせず、適切なサポートを行うのが何より大切です。それでは具体的にできるサポート方法を解説します。
無理に登校させない
心の不調を抱える子どもにとって、無理な登校はかえって負担を大きくします。新学期の登校初日に学校へ行きたくないサインに気づいた際は、登校を強いるのではなく、今の状態を受け入れお子さんの話を聞いてあげると安心感を与えられます。不安や焦りを抱えてしまう親御さんの気持ちも分かりますが、まずはお子さんが心を休める時間を確保すべきです。
子どもの気持ちに寄り添い、話をじっくり聴く
お子さんの不安や辛さを理解するには、まずは親が落ち着いて話を聴くことが欠かせません。感情を否定せずに受け止め、無理に答えを求めない姿勢が信頼関係につながります。そしてお子さん自身も気持ちを整理できます。
また子どもの話を落ち着いて聞くためには、親御さんがご自身を責めないようにすべきです。お子さんの不調は誰のせいでもありません。原因探しにやっきになり「育て方が悪かった」と自分を責めたり、家族内で責めあったりして家族関係が悪化すると、お子さんのストレスをさらに増やしてしまいます。
つらいとき、大変なときだからこそ、家族で支えあい協力しあうのを忘れないようにしてください。
生活リズムを整えるサポートをする
休養が必要な時期だからこそ、生活リズムの改善、維持は心身の回復に大きな影響を与えます。早寝早起き、規則正しい食事などを親御さんも一緒に整えてあげると徐々に安定した生活リズムを取り戻せるようになるでしょう。「親御さんと共に行う」とお子さんにも安心感を与えられます。
学校や専門家と連携する
家庭内で悩みを抱え込むのはよくありません。学校や専門機関と連携するのも検討しましょう。お子さんと話した内容をメモした上で担任やスクールカウンセラーと相談すると、お子さんに合った対応策を考えてもらいやすいです。また必要に応じて専門家の意見を仰ぐことも検討しましょう。
この際、お子さんときちんと話し、お子さんも親御さんも双方が納得した上で進めていってください。親御さんが勝手に話を進めると、お子さんの不信感を募らせてしまう危険性もあるので注意しましょう。
新学期の不安解消法5選
先ほどお話した通り、新学期に不安を抱えるお子さんは少なくありません。しかし事前の準備や日々のサポートによってその不安をやわらげられます。ここでは家庭で実践できる5つの具体的な対処法をご紹介します。
休み前の学習内容を振り返っておく
前学期の学習内容を思い出し、新学期の授業に対する不安を軽減しましょう。分かりやすい参考書やドリルを活用して自主学習を促しながら復習を進めると、勉強に対する自信も育ちます。
また親御さんはまずお子さんが自身で学習した事実を褒め、さらにできるようになった事柄を具体的に褒めてあげると、お子さんのやる気の向上や新しく学びを得る意欲の向上にもつながります。
時間割や行事予定を事前に確認する
新学期や新学年になった際、何がいつあるかを把握するだけでも先の見通しが立ちやすくなります。時間割や行事予定を親子で一緒に確認しておき、お子さんの気持ちを落ち着かせてあげましょう。予定を月ごとに紙に書き出すのも効果的です。
通学路や教室の場所をあらかじめ確認しておく
新しい環境に対する不安は事前の行動で大きく減らせます。登校日前に通学路を一緒に歩いてみたり、教室の場所を一緒に確認しておいたりすると、初日の緊張はとてもやわらぎます。特に新入生や転校生に対し効果的な準備となるでしょう。
達成しやすい小さな目標を立てる
学校へ行きたくないと感じ始めたお子さんに対しては「毎日教室に入る」「とりあえず1時間だけ授業に出てみる」などを、学習面が不安なお子さんに対しては「問題集を1日何ページ毎日続ける」など達成可能な目標をなるべく細かく設定し成功体験を積ませてあげましょう。
また、設定する目標は本人と話し合いながら決めてください。納得感が生まれ、本人が取り組みやすくなります。
持ち物や手続きを親子で一緒に準備する
持ち物の準備や提出物の確認などを親子で行うのも不安の軽減につながるでしょう。やるべきことをひとつずつクリアする過程で、お子さんも徐々に心の準備が整います。また「親子で一緒に取り組む」時間がそのままお子さんの安心感につながります。
関連記事:新学期の不安を和らげる!子どもを支える親の心得について詳しく解説!
親の不安にも寄り添う相談窓口
お子さんが不登校やひきこもり状態になると、親も不安や孤独を抱えがちです。その際は一人で悩まずに信頼できる相談窓口を利用すると、気持ちが軽くなったり、より冷静にお子さんと向き合えたりするようになるでしょう。保護者自身が安心できる相談環境があればお子さんへの適切な支援にもつながります。では具体的にどこに相談できるのかを解説します。
教育相談窓口
各自治体の教育委員会には保護者向けの教育相談窓口があります。学校生活や学習の悩み、進路の不安など幅広い相談に対応しており、専門的な視点での助言を受けることが可能です。まずは地域の教育委員会に問い合わせてみましょう。
学校の担任やスクールカウンセラー
学校には担任教師やスクールカウンセラーなど相談できる人がいます。お子さんの学校での普段の様子を知っているため、一人一人の状況に応じた支援や調整をしてくれる可能性があります。スクールカウンセラーは、親御さんの気持ちにも丁寧に寄り添いながら対応してくれるため、早めに相談してみるのが良いでしょう。
子ども専用の電話相談
24時間子供SOSダイヤルのような電話相談窓口を利用するのも一つの手です。ここはお子さんが気軽に悩みを話せる場として提供されています。またお子さんだけでなく保護者からの相談にも対応している場合があります。匿名で話せるため相談へのハードルが低く、また深夜や休日でも利用できるのが強みです。緊急時にも心強い支えになります。
全寮制のフリースクール
家庭内ではもちろん、教育委員会や学校などの相談窓口でも解決が難しかった場合には、「全寮制のフリースクール」を検討するのも良いでしょう。フリースクールでは学習支援や生活指導を通じてお子さんが自信を取り戻せるよう、専門スタッフがきちんとサポートしてくれる環境が整っています。長期的な見守りが可能なのも強みです。
新学期が辛いなら第三者に相談をしよう
子どもが新学期に対して強い不安を感じている際、家庭内だけで解決しようとすると親子ともに心が疲弊してしまいがちです。そんなときは家庭内で抱え込まずに第三者の力を借りるのも一つの方法です。学校や地域の相談機関、医療や心理の専門家など、子どもと保護者を支える体制はいつも整っています。家族以外の視点が入れば見えなかった課題や解決の糸口が見つかるケースも少なくありません。
もし学校や外部の機関に相談しても解決が難しかった場合は、チャレンジスクールをご検討ください。チャレンジスクールは「全寮制のフリースクール」です。不登校の子どもたちを支援する全寮制の環境を整え、子供たちの学びの場を提供する、そして自己肯定感を取り戻すサポートを行っています。まずはお気軽にご相談いただければと思います。



